HOME> 便利帳 >彫刻内容の傾向
内容いろいろ
彫刻内容は時節を映します。
洋型墓石が普及し始めた頃は「○○家」が一般的でしたが、その後「愛」「和」「夢」など一文字のものが多くなり、デザイン墓が広まると「ずっといっしょだよ」「Love Forever」などのオリジナルの言葉、夫婦の実家が合同で建てる両家墓には「××家・○○家」「和」「やすらぎ」など両家の結びつきを現し、そして震災後には「絆」やつながりを表す言葉が増えました。
戒名の彫り方
時節を反映するのは言葉だけではありません。
かつて戒名は棹石・上台・墓誌などに彫ることがほとんどでしたが、昨今の関東圏の霊園では一区画の墓地面積が狭いため、墓誌スペースが確保できなくなる等の制約の結果、フタ石や拝石に彫ることが珍しくなくなりました。
つまりこれまで和型なら約63センチ・基本的な洋型なら約45センチ程の石の高さ内に戒名を彫刻していたものを、小さめのフタ石なら25センチ程の高さ内に彫刻するわけです。
この狭くなった彫刻エリアに「戒名+没年月日+俗名+享年」を収めるにはレイアウトが重要になります。
1・3・5番が基本形↓↓↓
-
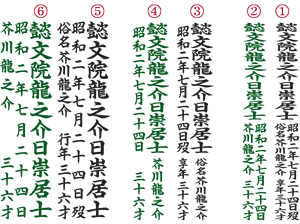
- ①②:従来型。人数確保できるけれど、ギュウギュウ詰め
- ③④:戒名の字数が多くても少なくても対応できる、バランスがとれたタイプ
- ⑤⑥:戒名の字数が多くても対応できる。人数があまり入らないので、石が横広タイプの方が良い
1・3・5番をさらにスッキリさせたものが、2・4・6番。
"没・俗名・享年"などを省略してあります。これは「墓誌に彫るのは"没・俗名・享年"に決まってる」→「わかりきった単語なら抜いてしまおう」というもの。
当家の方しか埋葬されないのなら「芥川龍之介」→「龍之介」 と名字を抜くことでさらに簡略化できます。
尚、二家が合同で建てる"両家墓"がなかった頃は、省略するなら「俗名」より「名字」でした。芥川家のお墓に芥川さん以外の方が入らないでしょう、という考え方です。
しかし現代は、建立後にどなたが埋葬されるか分かりません。
名字は入れておいたほうが無難でしょう。
当家由来・家系図
「××家由来」の彫刻箇所について相談をうけます。
当家のルーツから、両親の来歴・人となり・写真やサインなどの個人的なものまで、彫刻内容は様々。
-
彫りたいけど他人に読まれ放題なのはちょっと…という場合のおすすめは
- ・墓誌の裏面
- ・フタ石の裏面 または 納骨堂の内側の壁
- ・銘板に彫刻→その銘板を納骨堂内に収める
特に納骨堂は「開けたときに当家の方だけが読める」「子孫の代でもフタを開ければ、そのルーツを再確認できる」 というのがポイントです。
そのような機会にも当家由来を彫刻されてはいかがでしょうか。